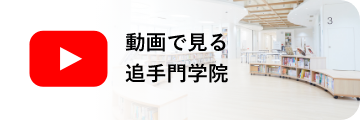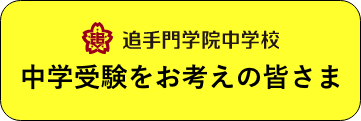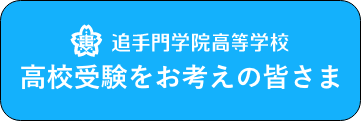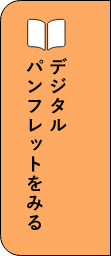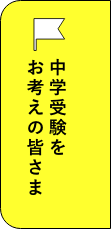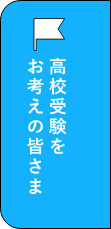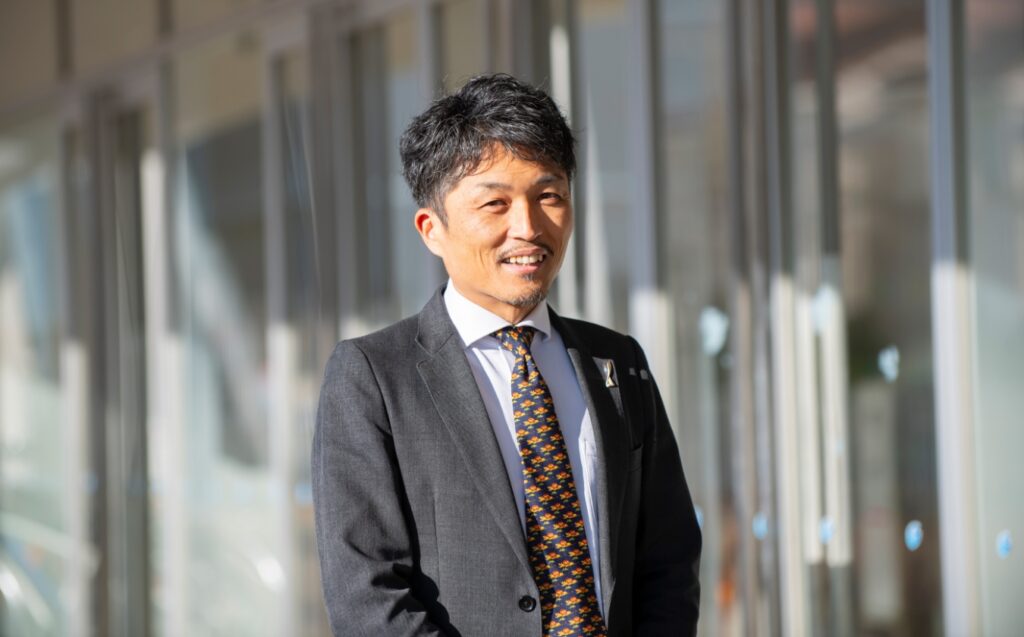入学から卒業まで
3年間通して取り組む
「修学旅行プロジェクト」
中学3年生で行く修学旅行に向けてスタートした新しいプロジェクトです。修学旅行を3年間のテーマとして取り組んでいる学校も少ないと思うので、それが一番の特徴かなと思っています。
私自身が学年主任を任され、定期考査に代わるプロジェクトの中身を考えていくようになった時に、最初に考えたのは生徒たちが「自分ごと」にしやすいテーマは何かということでした。学校生活の中で一番夢中になれるものって何なのかなと考えた時に、修学旅行ではないかと思いました。「修学旅行」はよく集大成の場と言われたりしますが、通常の学校での修学旅行への向き合い方は、現地に関する事前学習を直前に数コマ行い、体験・振り返りという階段状で終わることが多いように思います。そうなると結局、単発的なものというイメージが強いので、それならば3年間通した計画にしてしまおうと思い立ったわけです。
なぜ自分たちがそこに行くのか、そもそも場所の選択から始まって、その次に自分たちがそこに行くにあたって、どういうプロセスを踏めば行った時により主体的に参加することができるか。終わった後も、「行って楽しかった」という行動面だけを振り返って終わりではなくて、「現地の人って実際どうだったの?」ということを、言語以外の別のことでアウトプットできるような、そういう仕組みを作れないかなと思っています。3年間通して修学旅行をテーマにプロジェクトを進めていくことで、生徒たちにとって、より濃い体験ができるようにしたいと考えています。

1学期の課題は、
CM制作とポスター制作
まずは多面的に土地を知る
プロジェクト開始時は、入学して間もない頃でしたので友人関係もまだそこまでできていない段階で、まずはこの中で安心安全に過ごせるように、CM作りという形での取り組みをさせてもらいました。要は修学旅行の目的がまだ明確に分からないし、どういう力が身についていれば楽しく過ごせるのかというのが分からないので、そこをグループとして話し合い、「こういう力を身につけておきたいよね」という話をCM作りという形で進めていったのが1学期中間の課題でした。そして1学期期末には、近畿日本ツーリストさんにお越しいただき、行き先候補を発表してもらって、そこを深堀りしていくアプローチをしました。修学旅行の行き先候補は、世界自然遺産の国内4箇所と海外4カ国の計8箇所あります。各クラスを超えてチームを作り、ランダムに場所を割り当てていきました。「自然」「食」「アート」「お土産」という4つのテーマを設定して、割り当てられた地域や国について調べ学習をしていきます。その国・その地域にどういう自然があって、どういう食文化があって、というようなことを調べ学習していき、それを最終的にポスター制作の中でまとめるという課題でした。完成したポスターは校内に展示し、保護者の方々にはポスターセッションにも参加していただきました。
2学期は、大阪・関西万博に行って「文化」に焦点を当てていきます。文化の違いを感じることはもちろんですが、「日本人として日本で生まれる」こと、「韓国人として日本で生まれる」ことなど、国レベルだけではなくて個人にも文化があることを考えていきたいです。実際に留学生と外に出て、留学生が持っている文化を語ってもらいながらチームで校外学習をして「自分にとっての文化とは何か?」を考えてもらいたいと思っています。文化への思考を得た後、大阪・関西万博での展示の仕方や現地について調べた内容をもとに、3学期には「追手門修学旅行万博」を開催して、再度保護者の方々にも見ていただきたいと思っています。見てもらう人たちを「楽しませる」という視点も加えてパビリオン制作に取り組む予定でおります。

人と一緒に何かを作り上げる
共創の経験を通じて
自分の価値観や世界を広げてほしい
実際に現地に行った時に生徒たちがどう感じるかは正直行ってみないとわからないですけど、調べることと現地に行って吸収することってやっぱり違うと思います。私の経験を振り返ってみても、大学生の頃は「教育」を学びましたけど、実際現場に入ってみると座学で学んだこととは全然違います。ただ違う中でもどこか学んだ知識が引っかかってくるところもありますし、本物に触れることで、知識として持っていることとの違いもより鮮やかに認識できます。学んだこと全てが正解でもないですからね。現地に行って学んだことや知識がそういう風に繋がっていってくれればいいと思っています。
「理論としてはこう」だけど、リアルの場ではズレも生じてきます。考えることで、その部分を修正していくのは生徒たちの力です。その時に、自分の中である程度「こういうもの」というイメージがないと実際の判断はできませんから、そのために知識がやっぱり必要という話は授業でも繰り返していますし、やっぱりプロジェクトでも一緒かなと思います。
あと、プロジェクトに取り組む上で、生徒たちにもぜひ知ってもらいたいのは、何もかもが一人でできるわけではないということです。「何かを知り、何かについて考え、何かを共に創り上げる」。その過程では、対峙するテーマそのものだけではなく、自分のことやチーム内の他者のこと、他者を通して見た自分のことなどを双方向で知りながら知識や行動力を持って協力し向き合う姿勢が重要になります。これはどのような時代でも求められる力です。
「周りの誰か」の存在が、今の自分にない価値を広げてくれます。自分では知らなかった「新しい自分」を他者の力で感じることができるのです。それをプロジェクトの中で感じてもらいたいですし、だからこそ他者を大切に、そして「他者にとっての自分」を大切にしてもらいたいと思っています。