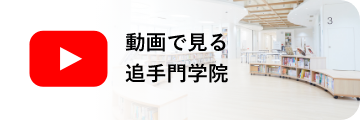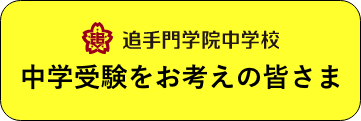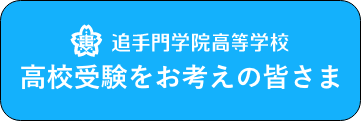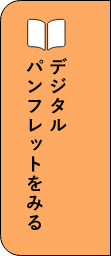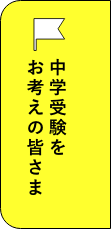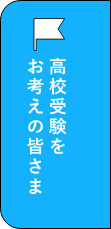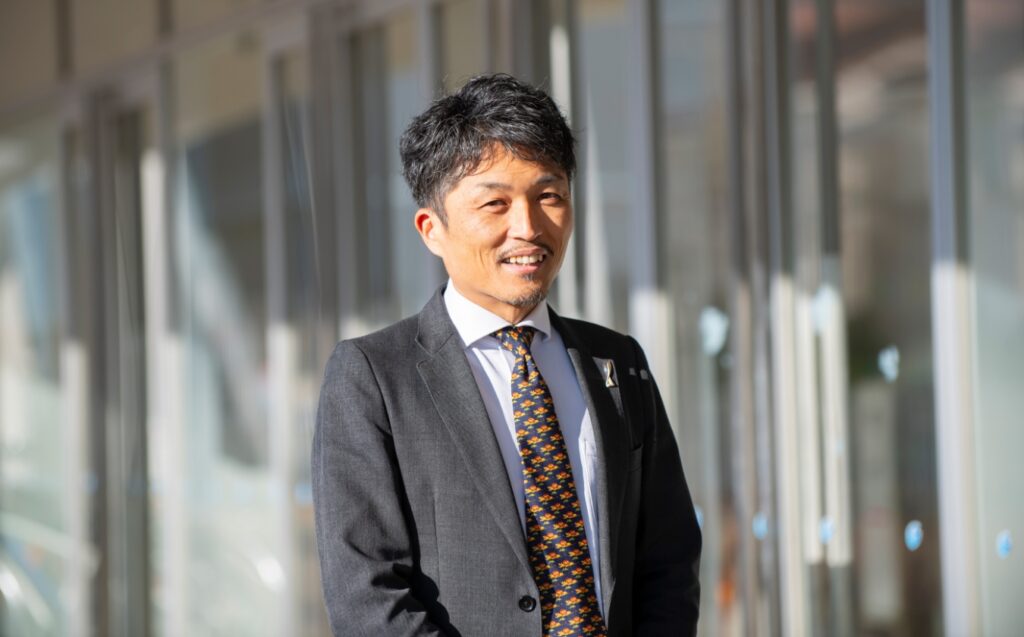伝統の丸郷班で取り組む
2泊3日のサイエンスキャンプ
我が校には、「丸郷活動」という独自の縦割り教育があり、異なる学年で作り上げられる班の中で、上級生が下級生をリードしながら話し合いをして、一緒に掃除や勉強をするなどの行動を共にすることで互いの学びを深めていく活動をしています。互いを承認するところからはじまり、傾聴・理解・共感の姿勢を養っていきます。
中学校のプログラムの1つであるサイエンスキャンプは、その丸郷班で取り組みます。今年は6月11日〜13日に実施し、中学1年生と2年生が箕面にて2泊3日の宿泊行事に参加しました。「五感で感じ、知り、考える」ことや「本物に触れる」経験を目的とし、非日常でしか味わうことのできない体験を通して学びの一つの在り方を考えていきます。サイエンスキャンプという名の通り、自然を取り扱い、活動を通じて好奇心を刺激し、新たな知識やスキルを学ぶ機会としています。また遊びと学び、知識と体験の融合を目指しています。

各班に分かれて、
ワクワクできる秘密基地作りに挑む
今回のキャンプでの大テーマは、「秘密基地を作ろう」というものでした。全部で20班くらいに分かれているのですが、それぞれに自分たちが1番ワクワクできる秘密基地を作ってもらうのが課題です。チーム内の意見を掛け合わせ、一つのものを創り上げる共創体験をしていきます。3日間の行程としましては、小さな模型を作りシミュレーションすることから始まり、木を切るための道具の扱い方を学ぶレクチャーや実践練習、土地探し、実制作の流れで進んでいきます。
まず初日に行った秘密基地の模型作りですが、割り箸を使って骨組みを組み立て、粘土で外壁を作り、紐を用いてアレンジを加えて基地のシミュレーションをしました。他者の作品を参考に、班の中で意見を交わして工夫を話し合い、基地のアイディアと構想を深めていきました。そして午後からは、宿舎の中に大きな丸太を持ち込んで木の切り方を学んでいきました。
2日目は、「知る」をテーマに班単位で自然の山を歩きながら、地形や環境を観察し秘密基地にピッタリの場所を探すことから始めました。どこが1番自分たちの秘密基地に適しているか。平坦な場所を選ぶチームもあれば、あえて斜面を選択したり、面白い形の土地を選んで基地の一部として活用したりと、各班で考えながら土地を選んでいました。場所が決まったら、早速基地作りの本番です。班で協力し自分達だけの秘密基地を「創って」いきます。素材を工夫したり役割分担をしたり、仲間と協力して皆それぞれに試行錯誤をしながら学校とは一味違った学びに没頭していました。
最終日は、成果発表会に向けて基地の仕上げをしました。山で拾った葉っぱを垂らして飾る等、各班でラストスパートを頑張りました。午後からは成果発表会です。三日間を通しての成果・学び・体験したことを振り返りながら発表します。基地の写真をスライドで写しながら、自分たちのこだわったこと、全員に見て欲しいポイント、苦労したこと等をプレゼンして伝えていきます。全ての班の発表が終わると、最後に投票という感じですね。想いや学びを言葉にすることで、この活動の総仕上げとしました。

失敗体験も大いに歓迎!
人生の経験値を増やして、
それぞれが輝くフィールドを見つけて
活動中は2年生が中心となって引っ張っていくのですが、自然が相手ですので、通常の授業とは勝手も違い、過酷な環境下に置かれることもあります。雨が降れば道がぬかるんで歩きにくいですし、日差しを避けるために木陰を探して進んだりもします。自然の中で遭遇する様々な問題に直面することで、解決策を自分たちで見出す経験を積んでほしいと思っています。危険だから何もやらせないのではなく、やり方を丁寧に教え見守ることで、困難を切り開くスキルと力強さを身につけてほしいです。もちろん、教育現場として安心安全な環境を整備しておくことは前提としています。
生徒たちには、成功体験だけを積んでほしいわけではないのです。火おこしに失敗した。カレー作りに失敗した。木登りに失敗した。こんな風に、むしろ大いに失敗をしてほしいです。その失敗は許されるものだからです。失敗したら「終わり」ではなく、たくさんの失敗を経験し工夫や改善を覚えることで、人生を粘り強く生き抜くための経験値を増やしてほしいと思っています。
また、そんな非日常の中で輝く生徒も出てきます。木を切るのが上手、野菜を切るのが上手、ロープワークが上手、昆虫に詳しい。いつもと違うフィールドだからこそ、学習や運動が苦手でも、分野ごとに輝く生徒に光が当たります。小さな変化を見逃さず認めることで生徒たちは更にイキイキと輝いてくれます。こういった側面もサイエンスキャンプの醍醐味かなと思いますね。
行事後には、協調性やコミュニケーション能力が向上して、異学年との繋がりも更に強固なものになります。下級生にとっては、それが学校で過ごす際の安心感にもなっていきます。上級生にとっても「去年を踏まえて今年はここを改善できた」など引っ張っていく側として、優しさやリーダーシップを発揮する良い機会になっているようです。