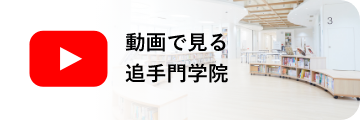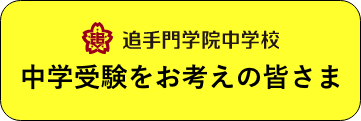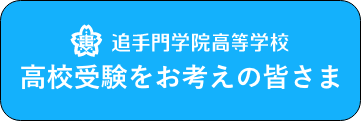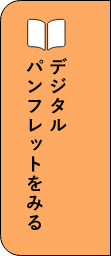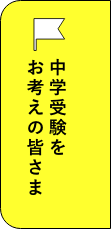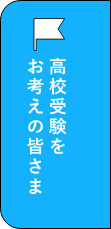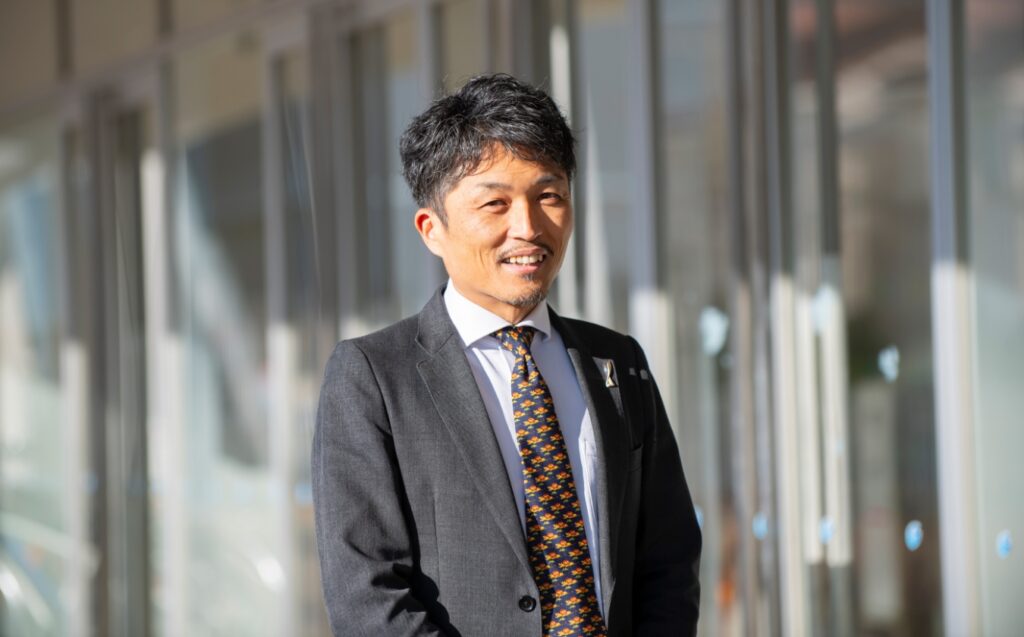海外からの短期留学生の受け入れで
全ての生徒に交流の機会と新たな視点を創出する
公教育機関の役目として、全ての生徒に国際教育の機会を届けることを意識しています。国際という観点では、海外研修や海外進学の機会を用意するのは当然ですが、それ以上に、そもそもそれらに興味のない生徒も含めて、実際に「海外の人たち」に接することで新たな視点を得られるよう、3年間のうちで1度は、海外の同世代と机を並べて学ぶ経験ができることを目指しています。そして情報に対する感度を高めるために、多種多様な経験の場を用意しています。
近年は、海外からの中高生ホームステイ短期留学を積極的に受け入れています。もともとコロナ禍にオンラインでつながった学校と、今ではリアルの場でスクールビジット等を通した交流をしている形です。今年度はアメリカ2件、インドネシア1件、フランス1件を予定しています。プログラムや日程も先方の希望と擦り合わせながら決めています。平和学習の一環で来られる学校もあれば、日本の学校文化を体験したいという目的の学校もあり、通常授業や書道体験、京都散策など色々なアプローチで交流を図っています。また、英語の授業限定にはなりますが、COIL(Collaborative Online International Learning)にも引き続き、力を入れています。
面白い授業の事例としては、創造コースの生徒とアメリカのジョージア州バルドスタ州立大学の学生との「コンビニプロジェクト」が挙げられます。バルドスタ州立大学近郊にリトル関西村ができたと仮定して、アメリカ人と日本人、どちらのニーズにも合うコンビニをデザインしてみるというプロジェクトです。初日はアイスブレイクから始まり、日本の生徒から日本のコンビニの魅力をマイクロプレゼンテーション(小グループ・短時間)を通してアメリカの大学生に伝えます。2日目には、アメリカ人側のニーズや観点を付加して「これはアメリカでも絶対に売れる」「これは日本でしか売れない」など議論を交わし、最終的に両方に好まれるコンビニをデザインしていきました。 生徒たちの反応もさまざまで、自分たちと同じ部分と違う部分、両方を感じられることが刺激となっているようでした。プロジェクトの回を重ねるごとに、自然にやりとりができるようになり、コミュニケーションを楽しんでいる様子も見られました。

中高生や留学生をハブにして
地域のつながりを強め、地域をもっと元気に!
地域コミュニティとの関わりという観点では、茨木市教育委員会や茨木国際親善協会、社会福祉協議会、地域の福祉法人や自治会と連携して各種イベントを行っています。地域の活動は、ユネスコ国際研究部が中心となってはいますが、一般生徒にも呼びかけをして、プロジェクトベースで人が集まる、いわゆるDAO(非中央集権組織)型の組織作りができつつあります。地域に中高生が入ることで、中高生がハブとなる地域コミュニティの活性を目指しています。高校生は高齢者から幼児に至るまで、絶対的な安心感を持つことのできる存在で、中高生の柔軟なアイディアを街づくりに生かすことができると考えています。
実際に一つの成功事例として、衰退傾向にある地域の神社の秋祭りに中高生の企画でたくさんの地域の子どもたち(およそ100名)を集めることができました。また、高齢化社会に関心を持っている海外の学生さんもいます。彼らにも地区の和太鼓クラブに参加してもらうなど、実際にコミュニティに入って経験し、日本社会の抱える問題も含めて、日本の「リアル」を肌で感じてもらうことが大切だと考えています。小さい子ども、元気な高齢者の方々、まちづくりに本気な大人たち。真の意味で「社会に開かれた学校」として、地域を繋げて元気にしていきたいですね。

グローバルとローカルのつながりを
「グローカル」として融合させる
これまでお話ししたように、今のところ「国際教育」と「地域連携」は、ぞれぞれのリソースを個別に積み上げている段階にありますが、目指しているのは「グローカル」。ゆくゆくは、国際教育と地域連携を絡めた活動をもっと拡げていきたいと考えています。すなわち海外から日本に来た人たちや、地域の大人・子どもといった、中高生が日常の学校生活の中でなかなか出会わない人たちと出会い、お互いの考え方を知り合い、一緒に何か新しいものを創る経験をする機会を設けることが最終ゴールです。
これは、海外からの学生(本校への留学生のみならず、大学への留学生を含めた)への対応も同じで、ホームルームクラスベースで授業等に入ってもらい、多数の生徒が海外の同世代と自動的に接することができる機会を設けるとともに、より意欲の高い生徒には課外で交流活動に参加できるような2段階に分けた仕組み作りを進めています。
フィールドを「今の自分に見えている世界」に限定しなければ、活躍の場が広がり、より「自分らしく」「なりたい自分」に近づくことができます。
見える世界が変わることで、思考が変わり、行動が変わる。頼られたり、必要とされたり、感謝されることで自分の存在意義を感じ、主体的に活動することができるようになるのです。また自宅でも学校でもないサードプレイス的なコミュニティに属することで、日常の自分に縛られず活動できるため、新たな可能性や社会的役割に気付く機会にもなるでしょう。このグローカルの取り組みが、同じ問題を抱える諸外国の先行事例にもなり得ます。もともと日本は、良くも悪くも「土地に縛られる」傾向があるので、地域のつながりが強い民族です。本校の取り組みが、地域のつながりを強めるモデルケースになったらいいですね。