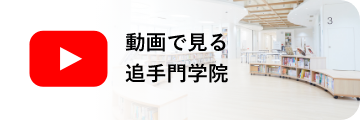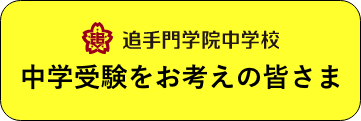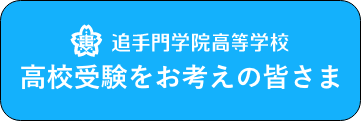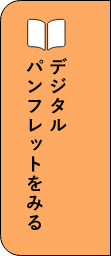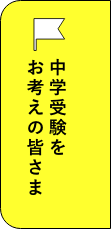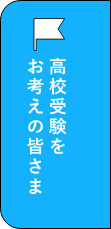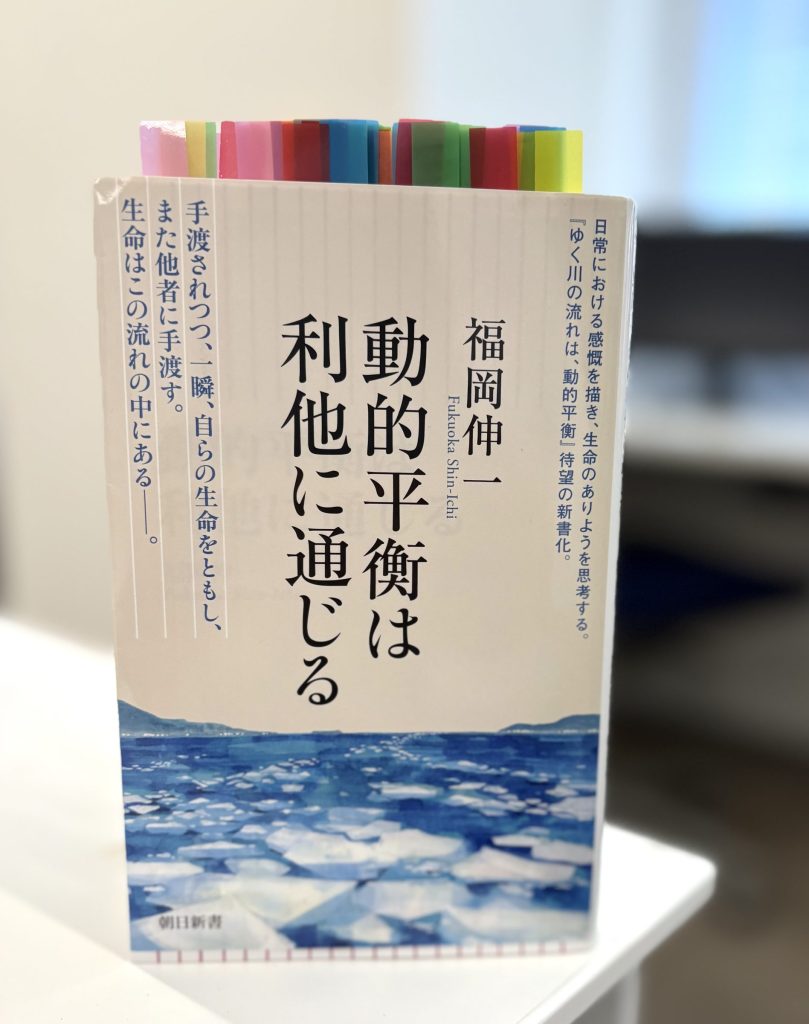
本日で1学期末考査とプロジェクトが終わり、そろそろ終業式の式辞の準備をしなければならない時期となりました。少し前の話になって恐縮ですが、1学期の始業式の日に全校生徒を前にして、「エントロピー増大の法則」に逆らって生きるという話をしました。その時に読んでいた、生物学者の福岡伸一先生の『動的平衡は利他に通じる』という本から一部引用しながら、私たちが生きるということの意味とか尊さを感じてほしいという話をしました。その後、数名の中学生から、あの話は面白かったです、と声をかけてもらいました。打てば響く生徒がいるのはとてもうれしいことです。
福岡先生の文章はいつも簡潔で、美しく、リズムがいいので、読んでいて心地が良いのです。写真の『動的平衡は利他に通じる』もすぐに読めてしまいますが、動的平衡について書かれた著作が他にもありますので、ぜひご一読を。
この本のタイトルにある「動的平衡」という概念をご理解いただくためにも、前書きのところから、引用してみます。
かつてフランスの哲学者アンリ・ベルクソンも、生命の本質を理解しようとして、その内部から生命を記述することを試みた。その結果、彼が得た答えは「生命には、物質が下る坂を登ろうとする努力がある」というものだった。生命の本質は”努力”である。細胞からなるのも、DNAを持つのも、呼吸しているのも、代謝しているのも、増殖するのも、無生物的な物質であれば、そのまま転がり落ちてしまう坂を、生命だけが登り返そうとする”努力”だと見抜いたのである。
では、坂を登ろうとする努力とは一体何か。100年以上も前に生きたベルクソンには、まだ十分な言葉の解像度がなかったのは仕方がない。しか彼の哲学は生命の本質をついていた。彼の言葉を現代的な科学用語で言い直せば次のようになる。「生命は、エントロピー(乱雑さ)増大の法則にあらがっている」
物質(非生命体)は、宇宙の大原則であるエントロピー増大の法則に身を委ねざるを得ない。秩序あるものは無秩序になる方向にしか変化しない。形あるものは崩れ、濃度が高いものは拡散し、高温のものは冷え、金属はさびる。建造物も長い年月のうちに傷み壊れゆくし、整理整頓しておいた机や部屋も散らかっていく。これはすべてエントロピーが増大する方向にしか物事は変化しないという法則の必然的な帰結である。エントロピーが増大する方向が、確率的・熱力学的に起こるべき方向だからだ。これが物質の下る”坂”である。
ところが生命だけは、この法則にあらがっている。なんとか”坂”を登り返そうとしている。無秩序になることに抵抗して秩序を作り出し、形のないところに形を作ろうとし、部分的に濃度の高い場所を生み出し、熱を産生する。酸化に抵抗して還元を行う。つまり、宇宙の大原則であるエントロピー増大の法則に抵抗を試みている。崩れることがわかっているのに石を積むことを諦めないギリシャ神話の英雄シーシュポスのように、あてどのない営みにあえて挑戦している。これが生命の”努力”なのである。
…生命科学は、いかにして生命が作られているかを詳細に究明し、大いなる成果を挙げた。ところが、21世紀になると、生命の持つ別の側面がクローズアップされてきた。それは、生命が、作ること以上に、壊すことを、一生懸命に、何通りもの方法で、休みなく行っているという事実だった。…
私はここに”努力”の秘密があるとわかった。
生命は、エントロピー増大の法則を「先回り」して、あえて自ら積極的に破壊を行っている。そのことでエントロピー増大の法則の進行を一瞬、追い越しているのだ。この局所的な追い越し分を使って、新たな秩序を構築している。つまりエントロピー増大の法則のスキをついて、”坂”を登り返している。
秩序はそれが守られるためにまず壊される。システムは、変わらないために変わり続ける。生命のこの営み、分解と合成という相反することを同時に行い、しかも分解を「先回り」して行うこと、これを「動的平衡」と呼ぶことにした。流れの中にあって絶えず動きつつ、危ういバランスを保つこと。動的平衡は、新陳代謝ではない。新陳代謝は、古いものが捨てられ、新しいものが作られるということだが、動的平衡は、新しいものでも積極的に壊すことに意味があるとする概念。こうして生命は、物質が下る”坂”を、—引きずり落されながらもー、何度も何度も登り返す。これが生きていることの本質であり、ベルクソンの言うところの”努力”なのである。
大変長い引用になってしまいましたが、福岡先生の動的平衡の概念を理解していただき、同時に彼の「名文」の世界に浸っていただくために、あえて長く引かせていただきました。私たちの生命について、私たちの所属している組織について考えるときのヒントにもなるかもしれませんね。